はじめに
こんにちは、皆さん!
先日、ご利用者さんの入浴介助をしていた時のことです。「このテープ、何か知っている?」と尋ねられました。それは認知症の貼り薬だと知っていた私は、少し得意げに「認知症のお薬ですね」と答えました。すると、「そうなの。私、認知症なんだって。旦那の名前も生年月日も知っているし、りんごの皮むきだってできるのになんで認知症なんだろう」と、ご利用者さんはひどく落ち込まれてしまったのです。
認知症と一口に言っても、その状態は人それぞれ。どう説明したら良いか分からず、私は「そうですね…」としか言えませんでした。あの時の、何もできなかった悔しさ。「もっと分かりやすく伝えられたら…」その思いから、今回は誰もが理解できる認知症の基本的な知識についてお話ししたいと思います。
一番大切なこと:ご本人の「真実」に寄り添う
まず、一番に知っておいてほしいのは、認知症と診断されたご本人が、誰よりも戸惑い、苦しんでいるということです。「なぜできないんだろう」「どうしてこんなことを言ってしまうんだろう」といったご自身の変化に、不安や混乱を感じています。その気持ちに寄り添うことが、私たちにできる一番大切なことなのです。
こんな事例がありました。
あるお昼休憩の時間、介護職員Bさんが他のご利用者さんと話していると、Aさんが「私、ご飯食べていないの」と話しかけてきました。Bさんは「Aさん!さっき食べましたよ!」と返しましたが、Aさんは「いや、私だけ呼ばれていないの」と続けます。Bさんが「私が部屋まで呼びに行って、一緒にご飯食べましたよ!覚えていないですか」と尋ねると、Aさんは「私が間違っていると思うの?」と問い詰めました。結局、Bさんは「そんなこと言っても、お昼ご飯は終わったので無理です。夕食まで我慢してください」と答え、Aさんは「私、本当に食べていないのに…」と寂しそうに顔を伏せてしまいました。
この話、介護職員Bさんの言っていることは事実として正しいですよね。Aさんは確かに昼食を食べました。でも、Aさんにとっては「食べていない」という感覚が紛れもない真実なのです。認知症になると、私たちには支離滅裂に聞こえることをおっしゃったり、同じことを繰り返し言ったりすることがあります。しかし、ご本人にとってはそれが全て現実。だからこそ、頭ごなしに否定せず、ご本人の感じていることを一旦受け止める姿勢がとても大切になります。
認知症ってどんな状態?お饅頭で例えてみましょう!
認知症と聞くと、なんだか難しい病気のように感じますよね。でも、実は身近な食べ物に例えると、とても分かりやすいんです。それは、お饅頭です!
お饅頭のあんこが、認知症の中核症状、そしてあんこを包むお餅が、**周辺症状(BPSD)**だと考えてみてください。
- 中核症状(あんこ) 脳の細胞が壊れることで直接的に起こる症状で、認知症の**「本体」**とも言える部分です。具体的には、新しいことを覚えられない(記憶障害)、**時間や場所、人が分からなくなる(見当識障害)**などがあります。あんこがなければお饅頭が成り立たないように、これらの症状が認知症の土台となります。
- 周辺症状(お餅) 中核症状によって引き起こされる、ご本人の心理状態や環境、人間関係などによって現れる様々な行動や心の症状です。お餅があんこを取り巻く状況によって形を変えるように、幻覚を見たり、何かを盗まれたと思い込んだり、落ち着きがなくなったり、やる気が出なくなったりすることがあります。これらは、ご本人の「困りごと」や「不安」が形となって現れていることが多いのです。
専門的な用語を並べましたが、「へぇ、こんな症状があるんだな」くらいで大丈夫ですよ!大切なのは、それぞれの症状がご本人のどんな「困りごと」から来ているのかを想像することです。
認知症の方への接し方のポイント
先ほどのAさんとBさんのやりとりから、どうすればよかったのか…そう考えた方もいるかもしれません。認知症の方と接する上で大切なのは、以下の3つのポイントです。
- 否定しない 先ほどの事例のように、ご本人の発言や行動を頭ごなしに否定したり、間違いを指摘したりするのは避けましょう。「それは違う」と言うのではなく、「そう思っていらっしゃるんですね」と一度受け止める姿勢が大切です。ご本人の世界観を尊重することで、安心感が生まれます。
- 受け入れる 認知症の症状は、ご本人の意思でコントロールできるものではありません。できないことや、混乱している様子を見ても、その状態を受け入れることが大切です。完璧を求めず、今できること、今感じていることを大切にしましょう。
- 介護サービスを利用する 認知症の方を否定せず、受け入れるのはとても難しいことです。それがご家族なら尚更でしょう。一人で抱え込まず、その時はぜひ人に頼ってください。デイサービスやショートステイなどの介護サービスを積極的に利用することも非常に重要です。ご本人が社会と繋がりを持ち続けられるだけでなく、ご家族の負担軽減にも繋がります。もし、どこに相談して良いか分からず、初めの一歩が踏み出せないのなら、皆さんの地域にある地域包括支援センターに連絡してみてください。必ず力になってくれますよ。
まとめ
認知症は、誰にでも起こりうる身近な病気です。しかし、適切な知識と接し方を知ることで、ご本人もご家族も、より穏やかな日々を送ることができます。お饅頭の例えのように、中核症状と周辺症状を理解し、何よりもご本人の気持ちに寄り添うことが大切です。
今回のブログが、認知症について考えるきっかけになれば幸いです。もし、ご自身やご家族のことで気になることがあれば、一人で悩まずに地域の相談窓口や専門家にご相談くださいね。
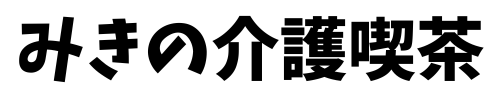
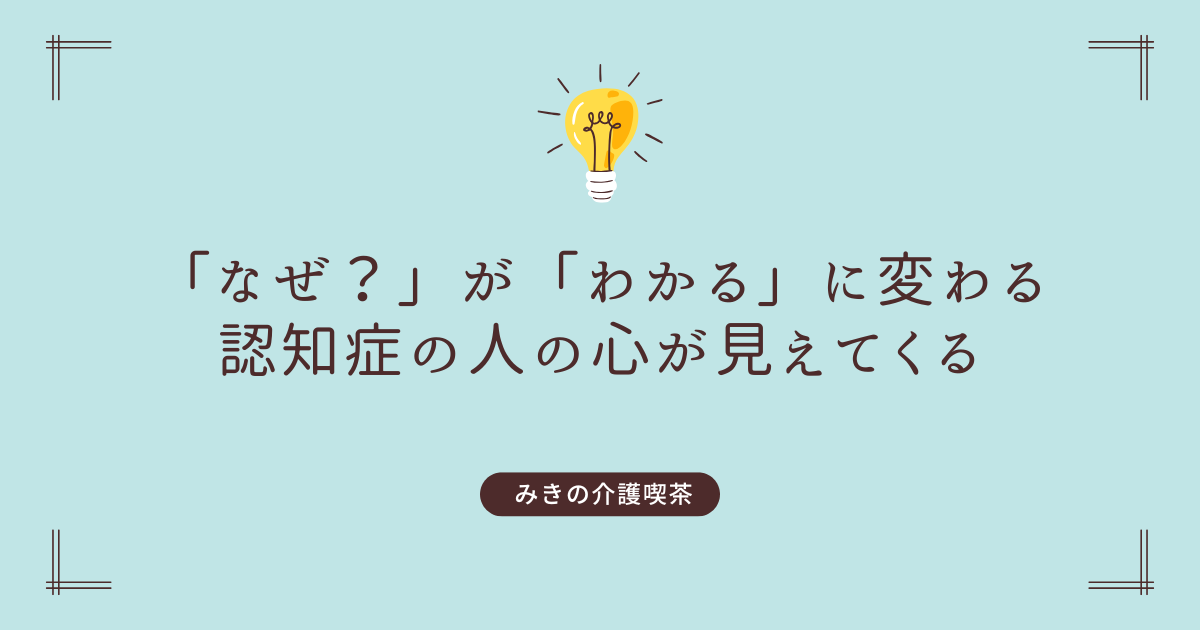

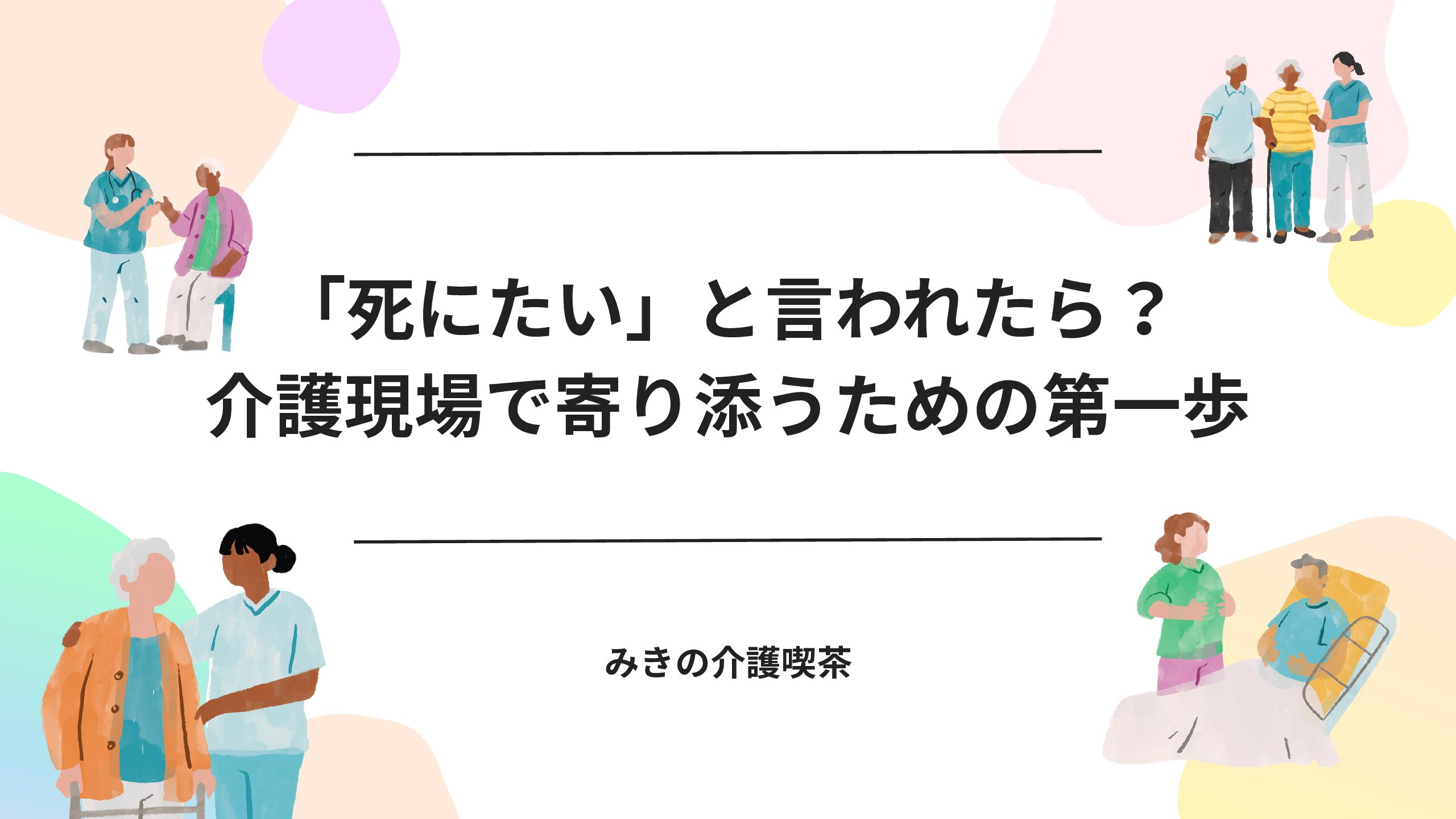
コメント