はじめに
皆さん、こんにちは!みきです!
今回は、介護疲れを軽減させる便利な福祉用具「スライデイングシート」をテーマにお話ししていきたいと思います!
聞いたこともない人も多いと思いますが、なるべくわかりやすく説明しますのでよろしくお願いします!

スライディングシートとは
利用者の体を移動・移乗するためのシート
低摩擦素材を使ったすべりやすい素材でできていて、摩擦を減らすことであまり力を使わずに移動介助が行える。

ツルツル滑るのー?
少し楽しそう!

すぐオモチャにしない笑
スライディングシートは万能で介護の仕事でもよく使います!

どこでよく使うの?

そうだね!
ベッドの上で使うことが多いよ!

使い方はこの後に説明するね!

はーい!
なぜ、体の負担を減らせるのか

これは「摩擦」が大きく関係してくるよ!

まさつ?

介護の仕事でよく聞く言葉があるんだけど「褥瘡(じょくそう)」または、
「床ずれ」って聞いたことあるかな?

難しい言葉だぁ・・・
聞いたことない・・・

わかったよ!
でも、とても大事なことだからしっかり覚えてね!
褥瘡とは、圧迫、摩擦、ずれ、浸軟といった外力により血流が途絶え、細胞や組織に障害をきたした状態。または「床ずれ」とも言われる。
中央法規 ケアマネージャー試験2023ワークブック 273ページから引用

まだ、難しい・・・

そうだよね!
ここでは「外部からの刺激で怪我になりやすい」と覚えてくれたらいいよ!

わかった!
でも、そんなに褥瘡って怖いものなの?

そうなんだ!
褥瘡になると治りが非常に遅いため「予防」が大切になるんだ!
褥瘡は「寝たきり」「座りきり」によってできます!
褥瘡になると治りが非常に遅いため、褥瘡にならないように「予防」することが大切!
発赤(皮膚が赤くなっている)ただれ、水疱(むずぶくれ)傷になっているなら整形外科の受診をお勧めします!
褥瘡(じょくそう)、床ずれになりやすい場所

褥瘡には「なりやすい場所」があるの知ってた?

知らなーい!
教えてほしい!!

了解!
わかりやすく説明するね!

上記のポイントでお話しした通り「寝たきり」「座りきり」の時に褥瘡ができやすくなります!
そのため、シチュエーションにわけて説明します!
褥瘡は圧迫されていることでなります。そのため、どこが圧迫されているのかしっかり把握することが大切です!
- 踵骨部(かかと)
- 仙骨部(お尻の上あたり)
- 肘頭部(肘の出っ張った所)
- 肩甲骨部
- 後頭部
- 外踝部(くるぶし)
- 膝関節部
- 大転子部(腰の出っ張り)
- 腸骨部(腰骨の出っ張り)
- 肘頭部(肘の出っ張った所)
- 肩峰部(寝具と肩が当たる所)
- 側頭・耳介部
- 尾骨部(尾てい骨)
- 仙骨部(お尻の上あたり)
- 腸骨部(腰骨の出っ張り)

医学用語が多いけど
覚えておくと便利だよ!

頑張ってみる・・・

時間がある時にネットで調べてみると
絵で説明しているものあるので、みてみてね!
体の負担を減らすのは介護する人にも関係する!

今まではご利用者さんに向けたお話しだったけど
介護する側にもメリットがあるんだ!

どんなメリットがあるの?

それは「腰痛予防」なんだ!

そうなんだ!
腰痛予防もしてくれるんだ!

そうなんだよ!
ベッド上で上下移動させたい時に「持ち上げなくていい」からね!

そうか!
低摩擦素材を使ったすべりやすい素材だったね!
ベッド上では、ご利用者を上下左右に動かす時があります。その時に活躍するのはスライディングシートです。
上記で説明した圧迫されやすい場所にスライディングシートを引くことによって、最小限の力でご利用者を移動させることができます!
スライディングシートは使い方を間違えると「ご利用者の残存能力を奪う」ことになります!
そのため、自宅で使用する場合は使い方をしっかり理解した上で使ってください。わからない場合は、介護職やケアマネージャー、地域包括支援センターに聞くか、ネットで調べていましょう!
まとめ
今回は「スライディングシート」についてお話ししました!
「スライディングシートを使うのがめんどくさい」「時間がかかる」など意見がありますが
まずは「安全に介護をすること」が大切です!
介護する人、介護される人が安全に取り組めるように、正しく使っていきましょう!
わからないことがあればメッセージで教えてください!
今日もありがとうございました!
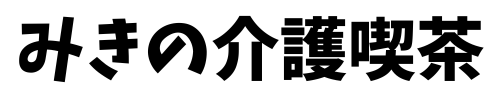


コメント