はじめに
近年、日本では自然災害が頻発し、私たち福祉施設の役割はますます重要になっています。「地域福祉への貢献」と「利用者様、そして地域住民の暮らしを守る」という大切な使命を果たすため、先日、BCP(事業継続計画)の研修を受けました。
研修を通して、改めて災害の恐ろしさを痛感しましたし、私たちの準備がまだまだ足りないことに気づかされました。しかし、グループワークで話し合う中で、「私たち小規模多機能型居宅介護だからこそできるBCPがある!」という確かな手応えを感じました。
その時の熱い思いと、私たちが考える具体的なBCPの形を、このブログにまとめました。実はこのブログ、AIの力も借りながら作成しています。ぜひ最後まで読んで、私たちと一緒に、災害に強い地域づくりについて考えてみませんか。
BCPとは?
BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)は、災害や事故といった緊急事態が起きた時でも、事業を止めない、あるいは早く元に戻すための計画です。
福祉施設にとってのBCPは、地震や津波、台風などの自然災害、あるいは感染症の流行、火事、システムの故障といった予期せぬ事態に直面しても、利用者さんへの介護サービスをできる限り続け、速やかに通常のサービス提供に戻すことを目指します。
特に、夜間の状況も考えておく必要があります。だからこそ、それぞれの施設に合わせたBCPの取り組みが大切になるんです。
なぜBCPが必要なのか?
災害が発生した際、福祉施設は利用者様の命と生活を守るための重要な拠点となります。介護サービスの継続は、利用者様だけでなく、そのご家族、そして地域住民の生活にも直結します。
- 利用者様の命と暮らしを守る: 災害時は、特に高齢者や障がいをお持ちの方々は、普段以上に支援が必要となります。BCPを策定することで、非常時においても安全を確保し、途切れることなく必要なケアを提供できるようになります。
- 地域福祉への貢献: 施設が災害時もサービスを継続できることは、地域の医療機関や他の福祉施設、住民の方々にとっても大きな安心材料となります。地域全体の防災力向上にも貢献します。
- 介護サービスの継続: 災害によって介護サービスが中断することは、利用者様の心身の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。BCPは、緊急時でも必要なサービスを提供し続けるための具体的な手順を定めます。
- 近隣事業所との連携: 災害時には、単一の施設だけでは対応しきれない状況も発生します。平時から近隣の福祉施設や医療機関、自治体などと連携体制を構築しておくことで、相互支援や情報共有が可能となり、より強固な防災・減災体制を築くことができます。
小規模多機能型居宅介護だからこそできる地域貢献とBCP
私たち小規模多機能型居宅介護事業所は、「通い」「泊まり」「訪問」という3つのサービスを柔軟に組み合わせる特性から、地域に根ざした密なケアを提供しています。この強みを活かし、災害時にも地域社会に大きく貢献できると考えています。
1. 災害時の具体的な貢献
災害時、当事業所は以下のような形で地域社会に貢献することを目指します。
- 要援護者への支援: 災害時にご家族を亡くされた方や身寄りのない高齢者、子どもの見守りなど、特に支援が必要な方々への一時的な受け入れや安否確認を行います。すべての方に対応することは難しいため、事前に町内会や自治体と連携し、支援の対象者や条件(例えば、当事業所の利用者様や地域住民で特に支援が必要な方など)を明確にしておくことが重要です。
- 情報拠点としての機能: 地域住民の方々への情報提供や、ボランティア活動の拠点となることで、地域の復旧・復興をサポートします。
2. 非常時、スタッフが取るべき行動
災害発生時、スタッフは以下の優先順位で行動します。これは、ご自身の安全が利用者様や地域への支援の土台となるためです。
- 自身の命を守る行動: まずは自身の安全を最優先に確保します。
- 家族の安否確認: 自身の安全確保後、速やかに家族の安否確認を行います。
- 利用者様の安否確認・安全確保: 家族の安否確認後、可能な範囲で利用者様の安否確認と安全確保に努めます。
- 地域貢献: 上記が完了した後、地域の状況に応じた貢献活動を行います。
3. 平時からの準備:地域との絆を深める
災害時にスムーズな連携を図るためには、日頃からの地域との関係構築が不可欠です。
- 相談しやすい事業所づくり: 地域住民の方が気軽に相談できるような、開かれた事業所を目指します。日頃から親しい関係を築くことで、いざという時に頼りやすい存在となります。
- 地域への役割の明示: 私たちが災害時にどのような支援や貢献ができるのかを、あらかじめ町内会や自治体と話し合い、共有しておきます。具体的な協力内容を事前に決めておくことで、混乱を防ぎ、迅速な対応が可能になります。
- 地域交流への積極的な参加: 町内のお祭りやイベントなどに積極的に参加し、地域住民の方々との交流を深めます。顔の見える関係を築くことで、信頼関係が生まれ、非常時の連携がより円滑になります。
今後の取り組み:利用者様と共に創るBCP
BCPは、事業所だけで完結するものではありません。利用者様や地域の方々との連携を深めることで、より実効性の高いものとなります。
- 利用者様と共に考えるBCP: ご利用者さんのご意見や希望をBCPに取り入れます。例えば、災害時に「こんなことができる」「こんなことで手伝いたい」といったご利用者さんの力を借りて、共に課題解決に取り組む姿勢を大切にします。
- 地域密着型の緊急対応: スタッフが各自の自宅から近い利用者さんを把握し、災害時に速やかに駆けつけられるような体制を構築します。これにより、勤務先の施設に無理に駆けつけるよりも、スタッフ自身の安全を確保しつつ、身近な利用者様への支援を優先することができます。
- ITツールを活用した安否確認: LINEなどのSNSを活用し、災害時のスタッフの安否確認を迅速に行える体制を整えます。これにより、状況把握の初動を早め、適切な人員配置や支援計画を立てることが可能になります。
【ご理解ください】 ここで述べた内容は、先日私がBCP研修を受けた際に、グループワークで「小規模多機能型居宅介護だからこそできること」として話し合い、共感したアイデアです。これらの取り組みは、現時点ではあくまで研修での学びと構想であり、実際に実施しているものではありません。今後のBCP策定や運用に向けて、具体的な検討を進めていく予定です。
BCPの取り組み:具体的な改善と今後の課題
BCP研修での学びを活かし、私たちは以下の具体的な対策と見直しを進めています。実際にやってみて初めてわかることも多く、今後の改善に繋げていきます。
1. 水の備蓄を見直し
ウォーターサーバーの水を、常に5本は備蓄するようにしました。水の賞味期限があることに気づき、新しいものと古いものに分けて管理し、古いものから使うようにしています。これにより、常に新鮮な水を確保しつつ、無駄なく備蓄を循環させることができます。
2. 避難訓練を実践的に
これまでは施設の駐車場までだった避難訓練を、実際に地域の公民館まで利用者さんと一緒に歩いて行ってみました。思った以上に距離があり、時間もかかることがわかりました。机上だけでは気づけない課題が多く見つかり、実際にやってみることの重要性を再認識しました。
3. 連絡体制を再構築
災害時の連絡体制について見直しを行いました。連絡網はありましたが、実際に訓練したことがなかったため、今回試しました。職員の中には電話番号を知られたくないという意見もあったため、前後の職員だけが連絡先を登録する形に変更し、個人のプライバシーに配慮しつつ、必要な連絡が取れるように工夫しました。
4. 避難経路と道具の確認
避難する際に障害物がないよう、避難口周辺の整理整頓を徹底しました。車椅子の方がスムーズに通れるよう、物が置かれていないか定期的に確認します。また、避難時に使う道具(例えば、避難用具や担架など)について、職員全員で確認し、使い方や保管場所を共有しました。
5. 消化訓練を楽しく実践
消火訓練を、利用者さんにも参加してもらい、レクリエーションのように楽しく取り組むことができました。これにより、利用者さんも防災意識を高めながら、もしもの時の行動を自然と身につけられるよう工夫しています。
これらの取り組みは、BCPの実効性を高めるために非常に重要です。実際に体験することで見えてくる課題を一つずつクリアし、より強固なBCPを構築していくことが私たちの目標です。
最後に
BCPは、私たちの地域における福祉サービスの継続性を確保し、利用者様と地域住民の皆様の安全と安心を守るための重要な柱です。私たち小規模多機能型居宅介護事業所は、地域とのつながりを大切にし、利用者様と共に、より実効性の高いBCPを構築していくことで、災害に強く、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現に貢献してまいります。
皆さんの事業所でもBCPについて考え、準備を進めていくことはとても大切です。小規模多機能型居宅介護事業所の強みを活かしたBCPについて、さらに具体的なアイデアがありましたら、ぜひ教えてください。
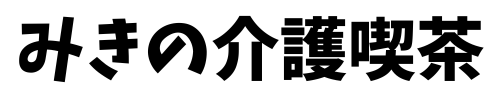
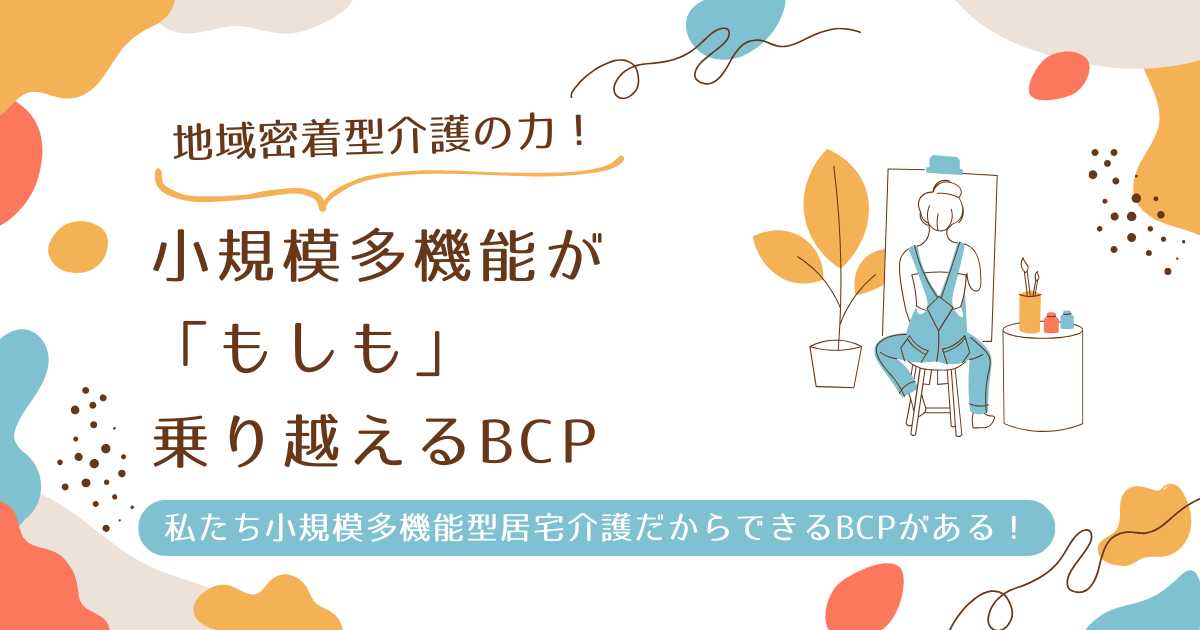
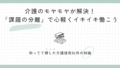

コメント