介護の現場でよく耳にする「臨機応変」という言葉。新人の頃、「ここは臨機応変に対応してね」と説明を受けて、戸惑った経験がある方も多いのではないでしょうか?
正直なところ、私も最初は「どうすればいいの?」と頭を抱えていました。でも、介護福祉士として6年目を迎え、少しずつその意味がわかってきた気がします。
今回は、そんな「臨機応変」について、私の経験を交えながら深掘りしていきたいと思います。
「臨機応変」って、そもそも何?
まずは辞書で調べてみましょう。
「臨機応変」とは、「その時の状況や変化に対応して、適切な処置をとること」とあります。
つまり、マニュアル通りにいかない状況で、その場に合ったベストな対応をすること、と言えるでしょう。
介護の現場で「臨機応変」が求められるのはどんな時?
介護は「人を相手にする仕事」です。そのため、あらかじめ決めていた予定通りに進まないこともしばしば。とにかく現場の状況を冷静に判断し、行動することが求められます。
例えば、デイサービスでの一幕を考えてみましょう。
ある日、利用者さんの熱が高く、ご自宅に送るべきか、施設で休んでもらうべきか迷う場面に遭遇しました。「熱が高いなら自宅に送るべきだろう」と普通は思いますよね。
しかし、ここに「独居」という情報が加わるとどうでしょうか?
高熱でまともに動けない方を一人でご自宅に帰すのは、非常に危険が高いと判断できます。この場合、近くにご家族がいらっしゃるなら施設まで迎えに来てもらうか、タクシーで病院を受診できるよう手配する、といった対応が冷静な判断となるでしょう。
このように、場所、人、時間、あらゆる情報を総合して判断するのが介護の現場になります。
緊急時に迷わないためにできること
「臨機応変」というと、すべてをその場の判断に任せるように聞こえるかもしれませんが、実はそうではありません。特に緊急時において、迷わず対応するためには「考えられる危険な状況に合わせてマニュアルを作成しておく」ことが大切です。
簡単に言うと、職員全員で会議を開き、予測される状況に対して、速やかに行動できるよう取り決めをしておくのです。そうすることで、いざという時に混乱せずに対応できます。
日常の「臨機応変」はどう考える?
ただ、「臨機応変」が求められるのは、危険な状況だけではありません。
車椅子を使用するのか、食事形態を変更するのか、施設の利用回数はどうするのか…考えるだけでもたくさんありますよね。これらすべてにマニュアルを作成していたら、今度は覚えることに必死になってしまい、かえって混乱してしまいます。
そんな時は、「判断する順番をはっきりさせる」ことを意識しましょう。
- 利用者さんがご自身の意思をしっかり伝えられる場合は、まず利用者さんの意見を最優先に考えます。
- 次に、現場の職員によるアセスメントと利用者さんの想いが異なる場合は、話し合い、お互いの意見をすり合わせます。
- それが難しい場合は、たとえそれが完璧な答えでなかったとしても、利用者さんに寄り添うことが大切だと私は思います。
また、日々の小さな変化に気づくことも、臨機応変な対応の第一歩です。例えば、食事介助中に利用者さんが急にむせてしまった時。決められた手順通りではなく、その方のペースに合わせて声かけを変えたり、体勢を調整したりするのも「臨機応変」な対応です。あるいは、レクリエーション中に利用者さんがいつもと違う反応を示したら、すぐに別の内容に切り替えることも。こうした日々の積み重ねが、大きな判断をする際の糧となります。
「臨機応変」の土台となるもの
「臨機応変」に対応できる介護職になるためには、いくつかの土台が不可欠です。
利用者さんへの深い理解
何よりも大切なのは、利用者さん一人ひとりを深く理解することです。その方の心身の状態、生活歴、価値観、好み、そして日々の小さな表情や言動に気を配ることで、いざという時の判断材料が増えます。表面的なマニュアル対応ではなく、その方に合わせた個別的なケアを提供できるようになるのは、この深い理解があってこそです。
チーム連携と情報共有
緊急時も日常のケアも、介護は一人で行うものではありません。職員間の密な情報共有とチーム連携が不可欠です。日頃から疑問や不安なことはすぐに相談できる風通しの良い職場環境を築き、互いの知識や経験を共有することで、より多角的な視点から「臨機応変」な対応を検討できるようになります。
私が大切にしていること
私が介護福祉士として介護の現場で働く中で、特に大切にしていることがあります。それは、できるだけ多くの介護技術を学ぶことです。
新人の頃、先輩職員から様々な介護技術を教えてもらいましたが、人によってやり方が違うため、「どれが正解なんだろう?」と悩んだことがありました。その時、上司に相談したら、こんな言葉をかけてくれたんです。
「それぞれの介護技術は全部正しいよ。それを使いこなせるようになることは、選択肢を持つということ。その時に一番合っている介護技術を提供できてこそ、介護のプロだよ」
この言葉を聞いた時の「ドキッ」とした感覚は、今でも忘れられません。
介護に「正解」はありません。決まった答えがあるなら、それは人ではなく、人形を相手にしているのと同じです。人を相手に仕事をしている以上、悩み続けるのは当然のこと。たとえ望ましい結果にならなかったとしても、その経験から何を学び、次にどう活かすかを考える。完璧を目指すのではなく、常に「より良い対応」を追求していく姿勢こそが、介護職の成長には欠かせないのだと思っています。
まとめ
「臨機応変」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、それは決して「勘」や「場当たり的な対応」ではありません。
多様な知識と技術を身につけ、日々の利用者さんへの深い理解とチームとの連携を土台に、冷静に状況を判断し、目の前の利用者さんにとって何が最善かを考え、柔軟に対応することが「臨機応変」の本質だと私は考えています。
この記事が、介護の現場で働く方々、特に新人の皆さんにとって、少しでも「臨機応変」を理解する手助けになれば嬉しいです。
皆さんは、介護の現場でどんな時に「臨機応変」を求められると感じますか? ぜひコメントで教えてくださいね。
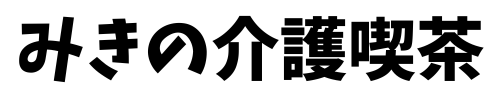
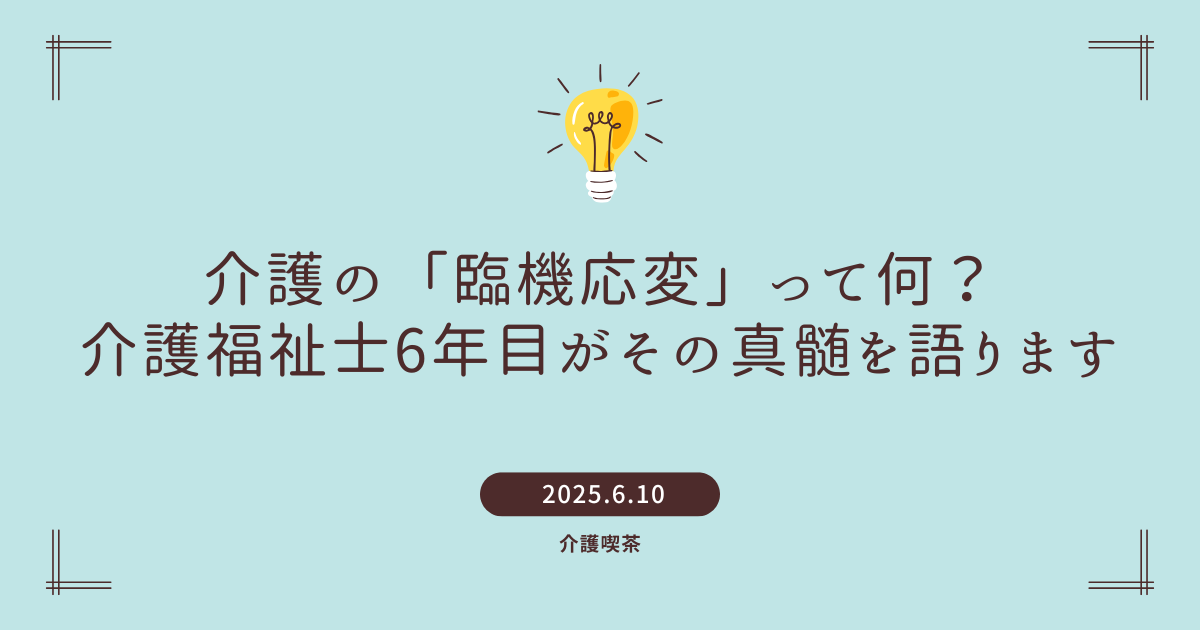
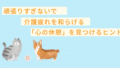
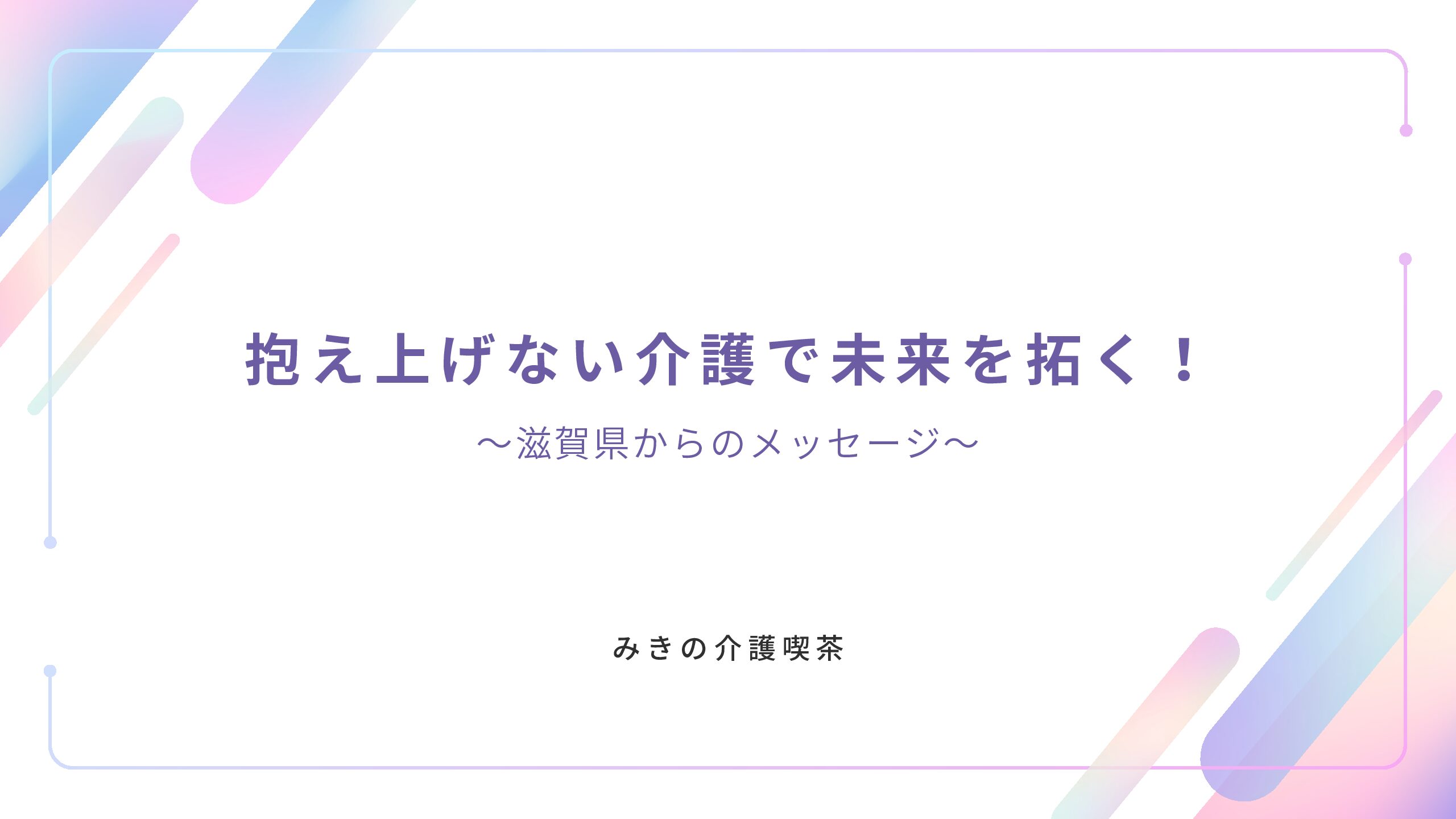
コメント