はじめに
はじめまして、皆さん。滋賀県在住、26歳の現役介護福祉士、ミキと申します。妻と可愛い子どもに囲まれ、日々を過ごしています。
この度、私のブログへお越しいただきありがとうございます。介護という言葉に、漠然とした不安や疑問を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。このブログでは、そんな皆さんの「?」に寄り添い、介護のリアルと、少しでも心が軽くなるような情報をお届けしたいと思っています。
私が介護の世界へ飛び込んだ理由、そして乗り越えてきた壁
私の介護への興味は、母がきっかけでした。介護経験がないにもかかわらず、働きながら資格を取り、ついにはデイサービスセンターを立ち上げるほどのパワフルな母の背中を見て育ちました。そのため、幼い頃から高齢者と触れ合う機会が多かった私にとって、介護の仕事はごく自然に興味を引くものでした。
しかし、ここで大きな壁にぶつかります。それは、親と子の考え方の違いでした。私は介護のことをもっと深く学ぶため、母の施設だけでなく、様々な場所で経験を積みたいと考えていました。ですが、家族、特に昔からの伝統を重んじる祖父は、私がすぐに母の仕事を継ぐことを強く望んでいました。何度も話し合いましたが、なかなか理解してもらえませんでした。
それでも、私は自分の信念を曲げず、なんとか家族を説得し、まずは養護老人ホームに就職することができました。これで自分の道を歩めると思った矢先、さらなる試練が訪れます。そこで私を待っていたのは、人間関係のひどい職場でした。職員間のいじめが横行し、私もその標的となってしまったのです。心身ともに追い詰められ、わずか3ヶ月で退職せざるを得なくなりました。
別の会社を探そうと考えていた矢先、今度は母が過労で倒れてしまいました。数度の家族会議の結果、私が母のデイサービスを手伝うことになったのです。その日から4年間、母の元で働くことになりますが、やはり私には「親の前で頑張る」ということが苦手でした。仕事に本気になれず、ふざけてしまうこともあり、当然、周りの職員からは冷ややかな目で見られました。当たり前ですよね。そんな自分が本当に嫌で、私は人生最大の決断を下しました。
それは、家を出るという選択でした。
この決断には、家族からものすごい怒りを買いました。精神が崩壊するほど追い込まれ、親戚中を謝罪して回るように言われたこともあります。しかし、私は自分の決心を曲げず、言い続けました。そんな辛い状況の中でも、私が腐らず前向きに進むことができたのは、妻と子どもの存在があったからです。どんな時も私を信じてついてきてくれた二人には、いくら感謝の気持ちを伝えても足りません。彼らがいたからこそ、私は今の自分になれたのだと心から思います。
家を出てからの挑戦と「抱え上げない介護」への取り組み
実家を出てから、私は「小規模多機能型居宅介護」で働くことを選びました。最初のうちは、それまでの辛い経験を忘れるかのように、ただひたすらに仕事に打ち込みました。同時に、心の回復のため、サウナや朝の散歩などを取り入れ、自分自身と真剣に向き合い続けました。そのおかげもあって、鬱症状になることなく、今も元気に働くことができています。
しかし、それだけではありません。何よりも、こんな私を温かく受け止めてくれた会社と、事情を問わず受け入れてくださった職員さんたちの存在が、私の心の大きな安定剤となりました。感謝の気持ちしかありません。
そして、その会社で働き始めて2年が経った頃、私は新たな挑戦をすることになります。それは、「抱え上げない介護」の導入です。私が就職する前から少しずつ取り組みは始まっていましたが、私が代表となってこの取り組みを推進していくことになりました。
人に伝えることの難しさ、組織を動かす方法、上司への報告で気を付けるべき点など、多くの壁にぶつかり、たくさんの失敗を経験しました。まるで、実家で甘えていた4年間を取り返すかのようなスピードで、様々なことを学んでいます。
それでも、私は決して一人ではありません。信頼できる仲間に相談し、支えられながら、この取り組みを諦めずに続けています。この挑戦を通じて、私は日々成長し、介護の現場をより良くしていくために邁進しています。
私が思う「介護」とは?〜「自由」という可能性〜
介護の仕事と聞いて、皆さんはどんなイメージを抱きますか?多くの方が「排泄介助、食事介助、入浴介助」といった、ご利用者さんと直接関わる場面を想像するかもしれません。もちろんそれらは介護の重要な一部ですが、私が思う介護はそれだけにとどまりません。私にとって介護とは、まさに「自由」そのものだと感じています。
介護の世界には、本当に様々な形で貢献しようとする人々がいます。例えば、音楽の力で現場を盛り上げたり、見た目も美しいペースト食のお寿司を作って食事の楽しみを届けたりと、多方面から介護をより良くしようと考えるプロフェッショナルたちがいるのです。
私自身も現在、「しがけあアンバサダー」として活動しています。若者たちに介護の仕事を職業選択の一つとして知ってもらうために、「しがけあフェスタ」への参加やラジオ出演など、積極的に情報発信をしています。このように、誰もが自分のできることを精一杯発揮して介護の未来を創ろうとしている。だからこそ、介護は固定概念に縛られない「自由な可能性」に満ちているのだと強く感じています。
正直なところ、私の中で「介護とは何か」という問いに対する明確な答えは、まだ見つかっていません。これからも様々な人との出会いを通じて、彼らの姿勢に触れることで、私の介護に対する考えもどんどん変化していくでしょう。それが、時としてたまらなく怖くもあり、同時にワクワクするほど楽しいのです。一つずつ、どんなことにも臆することなく挑戦し、時には失敗を繰り返しながら、いつか自分なりの答えを見つけ出すその日まで、私は走り続けたいと思います。
介護で一人で悩まないでください
これまでの道のりは決して平坦ではありませんでしたが、この経験があるからこそ、私は介護にまつわる様々な悩みや葛藤を理解できると信じています。
認知症の進行に戸惑うご家族、親御さんについ厳しくあたってしまう自分に落ち込む方。現場では、様々な「困った」に直面する方々を見てきました。そして、そんな悩みや苦しみを一人で抱え込んでしまう方がいかに多いか、痛感しています。
でも、どうか一人で抱え込まないでください。あなたの周りには、支えとなる存在が必ずいます。家族、友人、地域の支援者、そして私たち介護の専門家。頼ることは決して恥ずかしいことではありません。
このブログで伝えたいこと
このブログを通じて、私は皆さんの介護に対する不安を少しでも和らげたいと願っています。私自身の経験や知識を共有することで、「こんな時どうすればいいの?」「誰に相談したらいいの?」といった疑問に具体的なヒントを提供し、皆さんが一人で悩まずに済むよう、サポートできれば幸いです。
介護は、決して特別なことではありません。誰もがいつか、自分自身や大切な人が直面する可能性のあることです。だからこそ、正しい知識を持ち、必要な時に適切なサポートを得られるように、皆さんと一緒に考えていきたいのです。
どうぞ、お気軽にブログを読んでいただき、コメントやご質問もお待ちしております。皆さんの介護ライフが、少しでも明るく、そして穏やかなものになるよう、心から願っています。
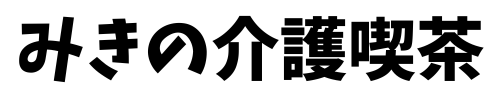
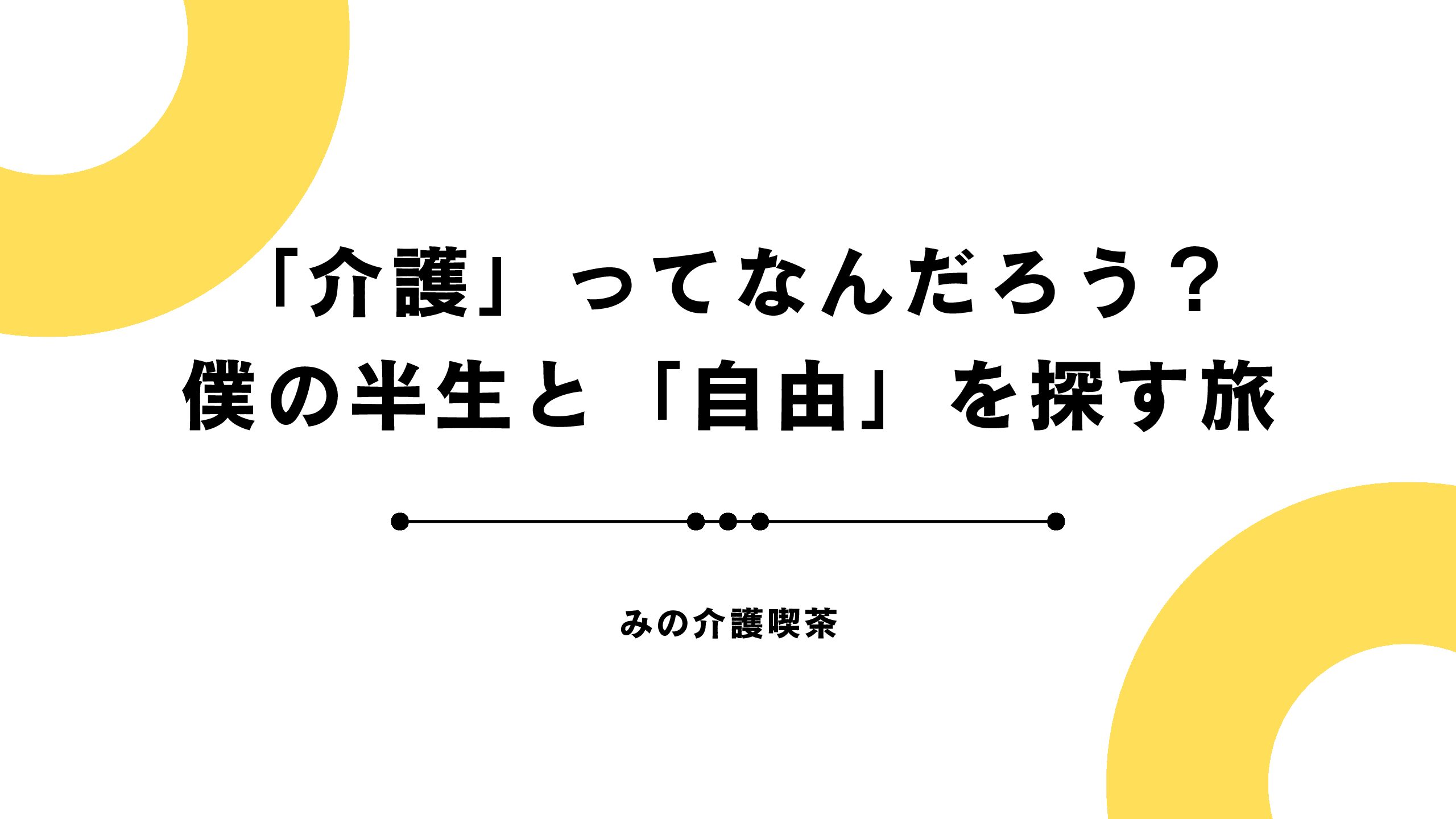
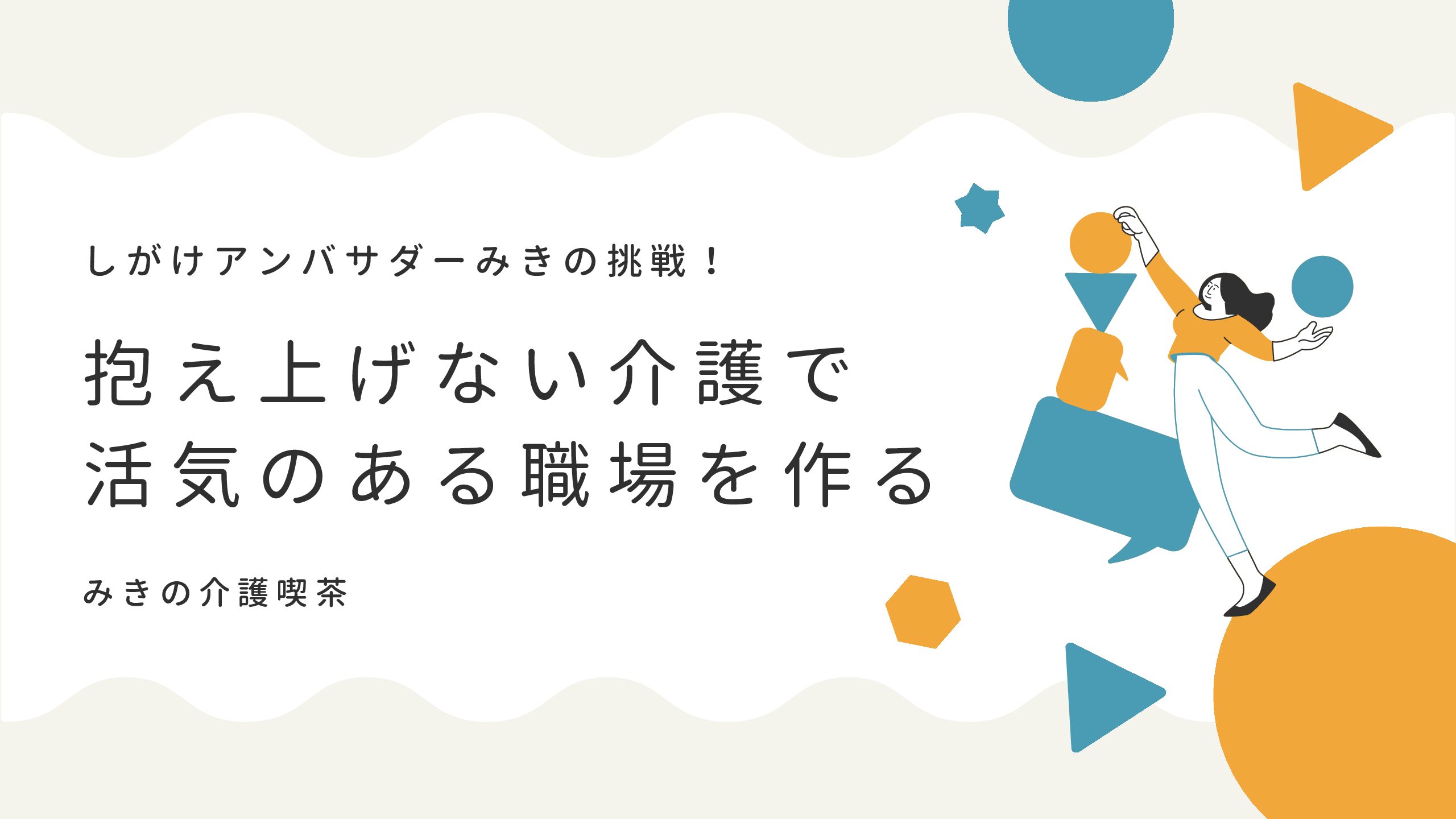
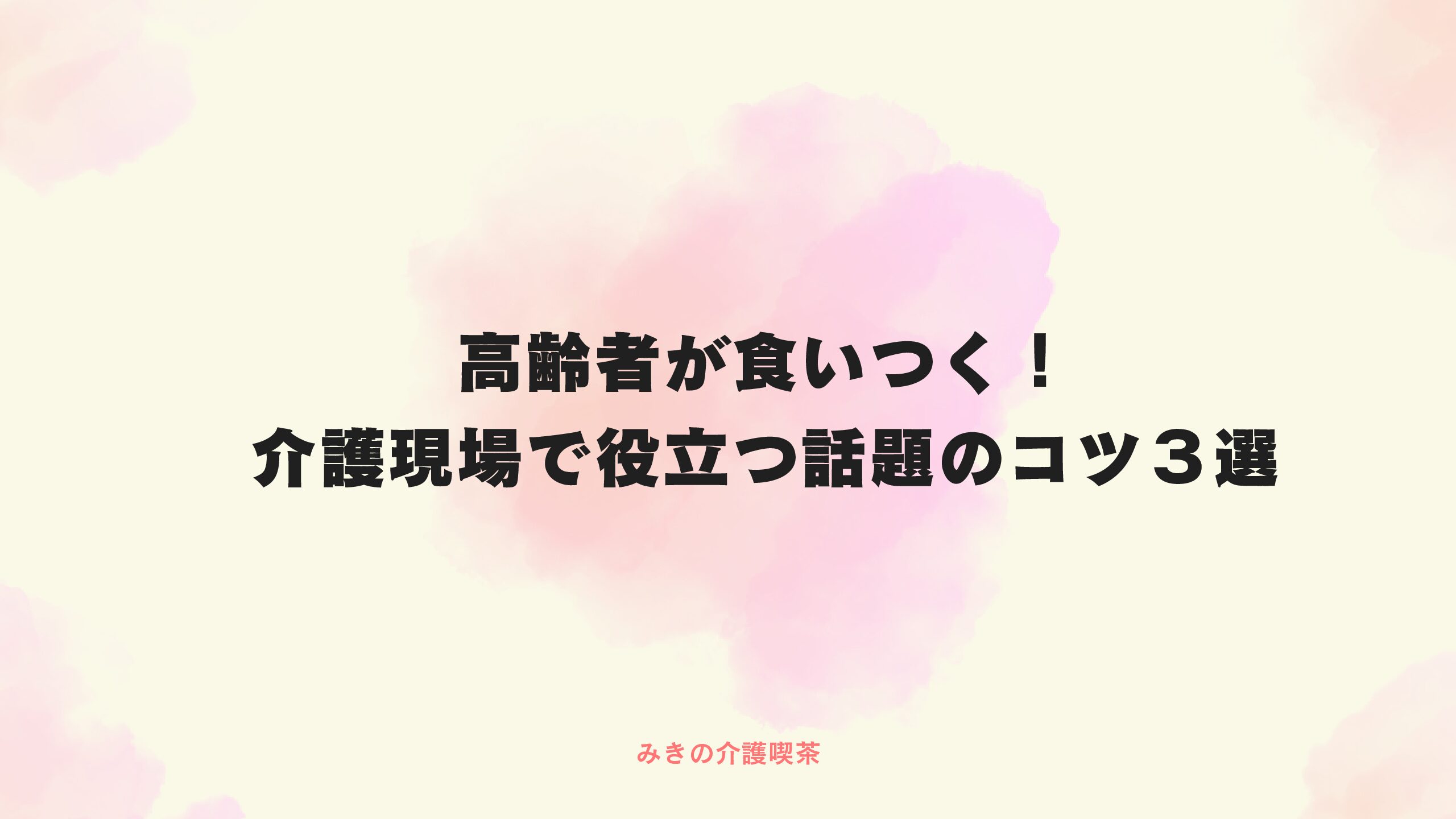
コメント