はじめに
今回は、職員の身体を守り、ご利用者様の身体的負担を軽減する「抱え上げない介護」への取り組みで経験した失敗と、そこからどのように改善していったのかをお話しします。滋賀県では「抱え上げない介護」と呼んでいますが、他県では「ノーリフティング」とも言われています。
失敗から見えてきた二つの大きな壁
私たちの施設で「抱え上げない介護」を推進する中で、二つの大きな失敗がありました。それは「ゴールの設定を間違えていたこと」と「所長とのコミュニケーション不足」です。この二つの壁が、当初の取り組みを大きく阻みました。
失敗その1:ゴールの設定を間違えていたこと
私たちの施設は10年以上前にリノベーションされた古い建物で、特にトイレ介助のスペースが狭いという大きな課題を抱えていました。高齢者のトイレ介助には、歩行器や車椅子、介助に必要なスペース、手すりなど、とにかく広さが必要です。しかし、当施設ではそれが十分でなく、職員が不自然な姿勢で介助せざるを得ないため、腰痛やぎっくり腰になるケースが後を絶ちませんでした。
この状況を早急に解決すべきだと考えた私は、スタンディングリフトの導入を所長に提案しました。しかし、許可は降りませんでした。理由は「アセスメントができていなかった」から。当時の私には、職員がすでに腰痛になり、ぎっくり腰になっているという現状があるのに、なぜアセスメントが必要なのか理解できませんでした。ご利用者様の身体能力を損なうことなく、職員の身体も守れるなら、断る理由が分からなかったのです。「そんなにゆっくりしていていいのか?」と焦りといら立ちが募るばかりでした。
導入断念と代替策、そして教訓
スタンディングリフトの導入は見送られましたが、私たちはこの課題を解決すべく、代替策を検討しました。ご利用者様の身体状況には日内変動があるため、その時の状況を判断し、立位が難しい場合はテープ式のおむつに変更し、ベッド上で交換するという方法を取り入れました。また、日中のトイレ介助は二人体制で行うことで、職員の腰への負担を大きく軽減できるようになりました。以前と比べて、腰痛の原因となる要因は確実に小さくなっていると感じています。
さらに、個人的な取り組みとして、トイレ介助後に実践できる腰痛リセット体操の導入も検討しています。これは、介助後に職員が自身の身体をケアする時間を持つためのものです。
- 足を平行に、肩幅より少し広めに開いて立ち、両手を腰の後ろの方(骨盤のすぐ上あたり)に当てます。この時、両手はできるだけ近くに揃えるようにします。
- 息を吐きながら前に押します。(腰を反らせるのではなく、手を当てた骨盤を前に押し込む意識で)つま先重心で、膝はできるだけ伸ばします。顎が上がらないように注意します。
- ゆっくりと息を吐きながら胸を開き、腰を反らせた状態を3秒間保ちます。
これを1から2回繰り返します。注意:体操中にお尻から太ももにかけて痛みが響いた場合は中止してください。
この失敗から得られた最大の教訓は、問題解決には、性急な結論ではなく、現状の丁寧なアセスメントと多角的な視点での検討が不可欠であるということです。自分の「こうあるべき」という思い込みだけでなく、様々な視点から物事を捉える大切さを学びました。
失敗その2:所長とのコミュニケーション不足
もう一つの大きな失敗は、所長とのコミュニケーション不足です。スタンディングリフトの件で焦りといら立ちが募った結果、つい会議の場で感情的に発言してしまいました。この感情的な発言が、所長との関係に大きな溝を作ってしまい、あっという間に最悪の関係になってしまいました。
その後、約1ヶ月間、職場で報告がスムーズにできないほどギクシャクした関係が続きました。これでは「抱え上げない介護」に取り組む以前の問題です。
関係修復への道のり
この状況を改善すべく、まずは周囲の信頼できる人たちに話を聞いてもらい、自分自身を見つめ直しました。そして、関係修復のために一歩を踏み出す決意をしました。
初めに私から謝罪しましたが、所長の態度は明らかに冷たいものでした。このままではいけないと課長に相談したところ、課長が私たち二人の間に入って話し合いの場を設けてくださいました。
その後、改めて謝罪し、改めて話し合う時間を頂けるように手書きの手紙を書くことにしました。Wordで書いたものを机に置くことも考えましたが、手書きの方が相手に見えない感情も伝わるのではないかと考え、丁寧に心を込めて書きました。紙もただのメモではなく、お店で売っている可愛らしいものを選び、少しでも誠意が伝わるように工夫しました。
そのおかげもあり、お互いの勘違いが解け、以前よりもさらに信頼関係が強くなったと感じています。この経験から得られた教訓は、いかに良い目的であっても、組織内で信頼関係を築き、建設的な対話を行うことの重要性です。感情的にならず、丁寧な対話を重ねることが、より良い協働を生み出すことを痛感しました。
共通の改善策と今後の展望
これらの失敗から得られた教訓を活かし、私たちは「抱え上げない介護」への取り組みを改善しました。
まず、「抱え上げない介護」の専門チームを結成し、チームで取り組む体制を整えました。そして、以下の明確な目標を設定しました。
「5年間で『職員の身体負担を軽減し、利用者の尊厳を守る「抱え上げない介護」を施設に定着させ、5年後には新人職員が自律的に学べる教育システムを構築する』」
5年後の目標達成に向けて、現在はチームで「抱え上げない介護」の具体的な介助方法やリスク管理について議論を深め、実践の場での検証を重ねています。今後は、この教育システムを他の部署にも広げ、施設全体で「抱え上げない介護」をさらに浸透させていくことを目指しています。まだまだ道のりは長いですが、職員とご利用者様双方にとってより良い介護環境を築くため、一歩ずつ着実に進んでいきます。
まとめ
「抱え上げない介護」への道のりは、決して平坦ではありませんでした。しかし、ゴールの設定の誤りやコミュニケーション不足という失敗から学び、チームで目標を共有し、何よりも大切なコミュニケーションを丁寧に行うことで、大きな改善へと繋がりました。今回の私たちの経験が、介護現場で働く皆さんのヒントになれば幸いです。
皆さんの施設では、介護現場での身体的負担軽減のためにどのような工夫をされていますか?ぜひコメントで教えてくださいね。
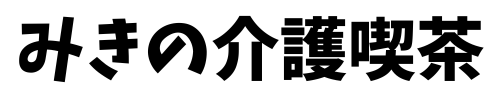
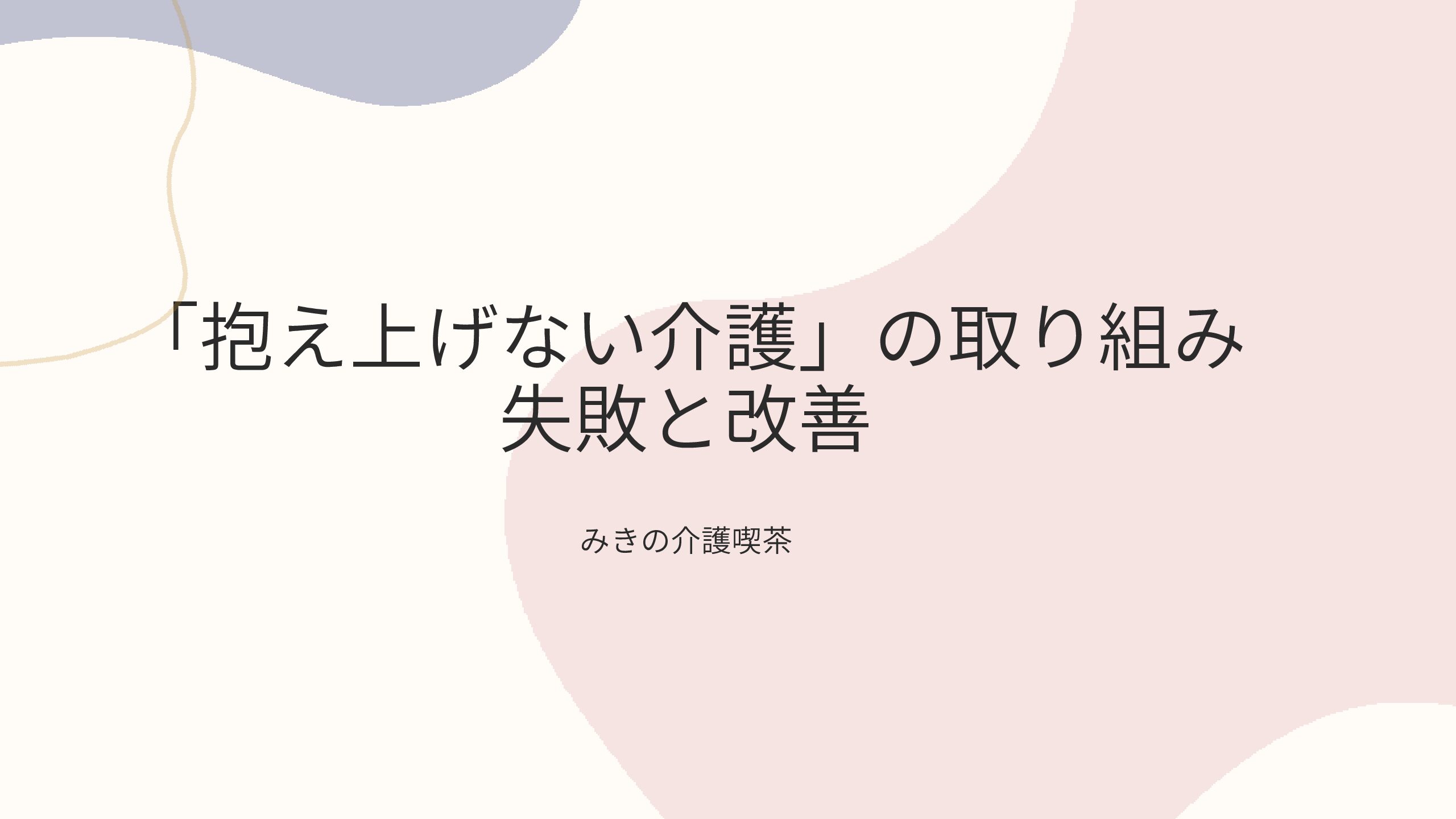
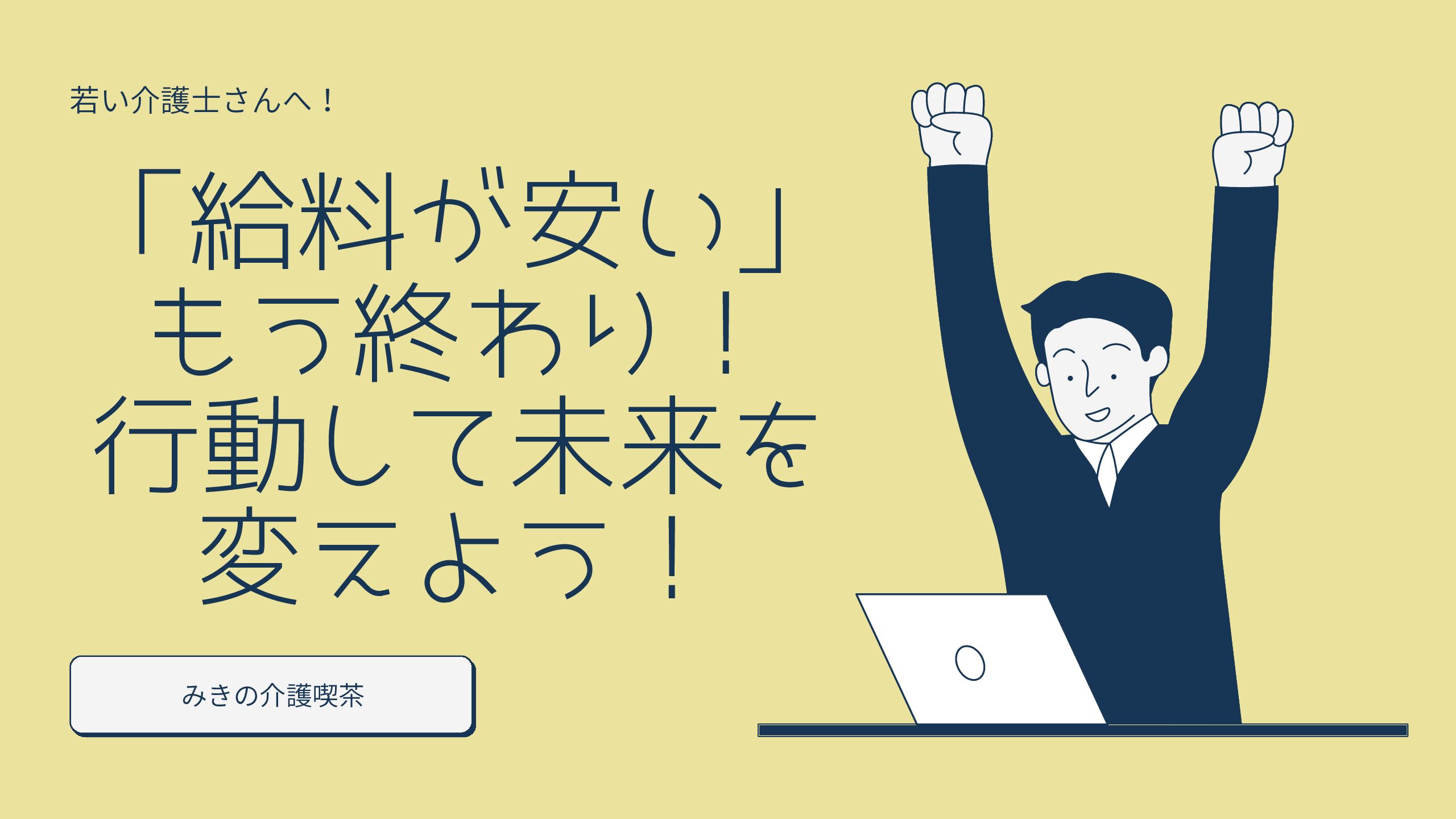

コメント