はじめに
先日、認知症基礎研修に参加し、無事に終了証明書をいただきました。介護の仕事を始めて7年。それなりに認知症について知っているつもりでしたが、改めて学んでみると、忘れていたことや驚かされることばかりで、久しぶりに眠くならずに受講できた研修でした(笑)。
今日のブログでは、研修で改めて「大切だと感じたこと」と「認知症と寄り添うための基礎」についてお話ししたいと思います。これは私自身の復習も兼ねていますので、少しお付き合いくださいね!
「認知症」ってどんな状態?
研修でまず印象的だったのは、「認知症は病気ではない」という言葉です。これは、認知症が特定の病名ではなく、さまざまな原因によって脳に変化が起こり、その結果として認知機能が低下し、日常生活に支障をきたしている状態(おおむね6ヶ月以上継続している場合)を指す、という定義がなされているからです。
少し難しい表現ですが、簡単に言うと、脳の病的な変化によって記憶力や判断力などが低下し、生活の中でサポートが必要な状態が続いていることを指します。
認知症の症状は、脳のどの部分が変化するかによって異なります。例えば、よく知られているアルツハイマー型認知症は、脳が全体的に萎縮することで、記憶障害や見当識障害(時間、場所、人が分からなくなること)が主な症状として現れます。
このように、単に「もの忘れがひどくなること」というだけでなく、脳の変化によって様々な症状が現れるのが認知症です。
4つの主要な認知症を知る
認知症には、主に以下の4つのタイプがあります。それぞれの特徴を理解することで、より深く認知症の状態を把握できるようになります。
1. アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症は、脳の神経細胞が減少し、脳が病的に萎縮することで起こります。残念ながら、その原因はまだ完全には解明されていません。
主な症状:
- 顕著な記憶障害: 5〜10分前の出来事を忘れてしまったり、同じことを繰り返し尋ねたりすることがあります。
- 見当識障害: 時間、場所、人が分からなくなり、例えば時計を見ても時間が理解できなかったり、自分の家や家族を認識できなかったりします。
- 判断力の低下: 適切な判断をすることが難しくなります。
- 実行機能障害: 複数の手順が必要な行動(例:買い物に行くために「9時に家を出て、自転車に乗り、電車に乗って、スーパーに行く」といった一連の動作)を計画し、実行することが困難になります。
2. 血管性認知症
脳卒中(脳出血や脳梗塞など)が原因で起こる認知症です。比較的急激に発症し(発作から3ヶ月以内)、症状が階段状に進行するのが特徴です。
主な特徴:
- まだら状の症状: 脳のどの血管が損傷したかによって症状が異なり、人によって出現する症状にばらつきがあります。
- 感情面の障害: 無表情になったり、感情の起伏が激しくなったりすることもあります。
3. レビー小体型認知症
レビー小体という特殊なタンパク質が脳の大脳皮質を中心に、中枢神経や交感神経など広範囲に出現することで起こる認知症です。脳の萎縮も伴います。
主な症状:
- 変動性の認知機能障害: 活発な時と、電池が切れたようにぼーっと一点を見つめる時が交互に現れるなど、日や時間によって症状の程度が大きく変動します。
- 幻視: 実際には存在しないもの(人や虫など)が見えることがあります。ご本人にとっては現実に見えているため、否定せずに耳を傾けることが大切です。
- パーキンソン症状: 小刻み歩行や体のこわばりなど、パーキンソン病に似た症状が現れ、転倒しやすくなることがあります。
4. 前頭側頭型認知症
言葉の通り、脳の「前頭葉」と「側頭葉」が萎縮することで起こる認知症です。
主な症状:
- 人格の変化: 以前は穏やかだった人が怒りっぽくなるなど、性格が大きく変わることがあります。表情も変化することがあります。
- 抑制の欠如: 衝動的な行動が増え、「欲しい」「食べたい」といった欲求を抑えられずに手を出してしまうことがあります。
- 社会性の欠如: 社会のルールやマナーが理解できなくなり、例えば店の商品を勝手に食べてしまうなど、してはいけないことの区別がつかなくなることがあります。
- 常同行動: 毎日同じ時間に同じ行動を繰り返すなど、特定の行動パターンを繰り返すようになります。
若年性認知症
65歳未満で認知症を発症した場合を若年性認知症と診断されます。日本では血管性認知症が最も多いとされていますが、上記で説明したどのタイプの認知症も若年性で発症する可能性があります。
認知症の方との「寄り添い方」の基本
認知症の多様な症状を理解することは大切ですが、それ以上に重要なのは、目の前の「人」として尊重し、その方らしい生活を支えることです。研修で学んだ、ご本人に寄り添うための基本的な心構えや、具体的な接し方のポイントをいくつかご紹介します。
1. パーソン・センタード・ケアの視点
「認知症は病気ではない」という導入部分でお伝えしたように、私たちは認知症のある方を「病気の人」としてではなく、その方の「個性」や「人生」の一部として受け入れ、ご本人が望む生活、ありのままの姿を尊重するケアの考え方です。認知症という状態にある「人」を理解し、その方の感情や意思、尊厳を守ることを第一に考える必要があります。
2. 日常での接し方「3つのない」
認知症の方との関わりにおいて、特に大切だと感じたのは、以下の3つの「ない」です。これは、認知症のタイプに関わらず共通して役立つ心構えです。
- 驚かせない: 突然声をかけたり、後ろから近づいたりせず、視野に入ってからゆっくりと声をかけましょう。
- 急がせない: 認知機能の低下により、物事を理解したり、行動に移したりするのに時間がかかることがあります。ご本人のペースを尊重し、焦らせないことが大切です。
- 自尊心を傷つけない: 失敗や間違いを指摘したり、子ども扱いしたりせず、本人の気持ちに寄り添い、できることを認める姿勢が重要です。
3. 心が通うコミュニケーション
認知症の方とのコミュニケーションでは、言葉だけでなく、非言語的な要素も非常に重要になります。
- ゆっくり、はっきりと、短い言葉で: 一度にたくさんの情報を伝えず、一つずつ丁寧に話すことを心がけましょう。
- 目線を合わせ、穏やかな表情で: 安心感を与え、心を開いてもらいやすくなります。
- 共感と傾聴: 幻視や妄想など、私たちには理解しにくい話であっても、まずは「そうなんですね」「大変でしたね」と受け止め、ご本人の感情に寄り添いましょう。否定せず、訴えに耳を傾けることで、不安や混乱が軽減されることがあります。
- 非言語コミュニケーションの活用: 笑顔や穏やかな声のトーン、優しいジェスチャーは、言葉以上に安心感を与えることがあります。相手が嫌がらない範囲で、優しく手を握ったり、肩に触れたりするスキンシップも有効です。
- 過去の経験や趣味に関心を持つ: ご本人の過去の生活や好きなことについて話を聞くことで、穏やかな表情が見られたり、コミュニケーションが円滑になったりすることがあります。
4. 安心できる環境づくり
認知症の方の不安や混乱は、周囲の環境によって引き起こされることもあります。ご本人が安心して過ごせる環境を整えることも、大切なケアの一つです。
- なじみの環境を大切に: 使い慣れたものや、見慣れた場所に囲まれていることで、安心感に繋がります。物の配置を大きく変えないようにするのも良いでしょう。
- シンプルで安全な空間: 物を整理し、探し物を減らすことで混乱を防ぎます。特に転倒のリスクを考慮し、段差をなくしたり、手すりをつけたりするなど、安全に配慮した環境を整えましょう。
- 適切な明るさと音量: 暗すぎず明るすぎず、ご本人が心地よいと感じる明るさを保ち、大きな音や騒音は避け、落ち着いた環境を提供しましょう。
5. 介護する側のセルフケアも大切に
介護は、精神的にも肉体的にも大きな負担を伴うことがあります。完璧を目指す必要はありません。一人で抱え込まず、時には休息を取ることも非常に重要です。地域の相談窓口や介護保険サービスなど、利用できる資源はたくさんあります。困った時には、迷わず専門家や周りの人に相談しましょう。
まとめ:認知症理解への第一歩
今回の研修で、認知症の基礎を改めて学ぶことができました。
今回ご紹介した4つの主要な認知症のタイプや症状、そして若年性認知症についても理解を深めることができ、さらに日々の介護において不可欠なご本人への寄り添い方についても具体的なヒントを得ることができました。これらは、介護に携わる者として、また一人の人間として、認知症の方々への理解を深める上で非常に重要だと改めて感じています。
認知症の**「中核症状」と「BPSD(行動・心理症状)」**は、ご本人やご家族、そして私たち介護者が日々直面する課題を理解する上で欠かせない要素です。これらを学ぶことは、認知症の方々が抱える困難を想像し、より適切なサポートを提供するための基盤となります。
次回は、その「中核症状」と「BPSD」について、さらに詳しく振り返っていきたいと思います。引き続き、私の復習にお付き合いいただけると嬉しいです!
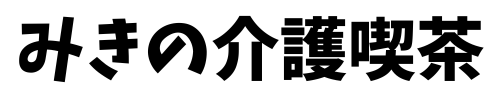
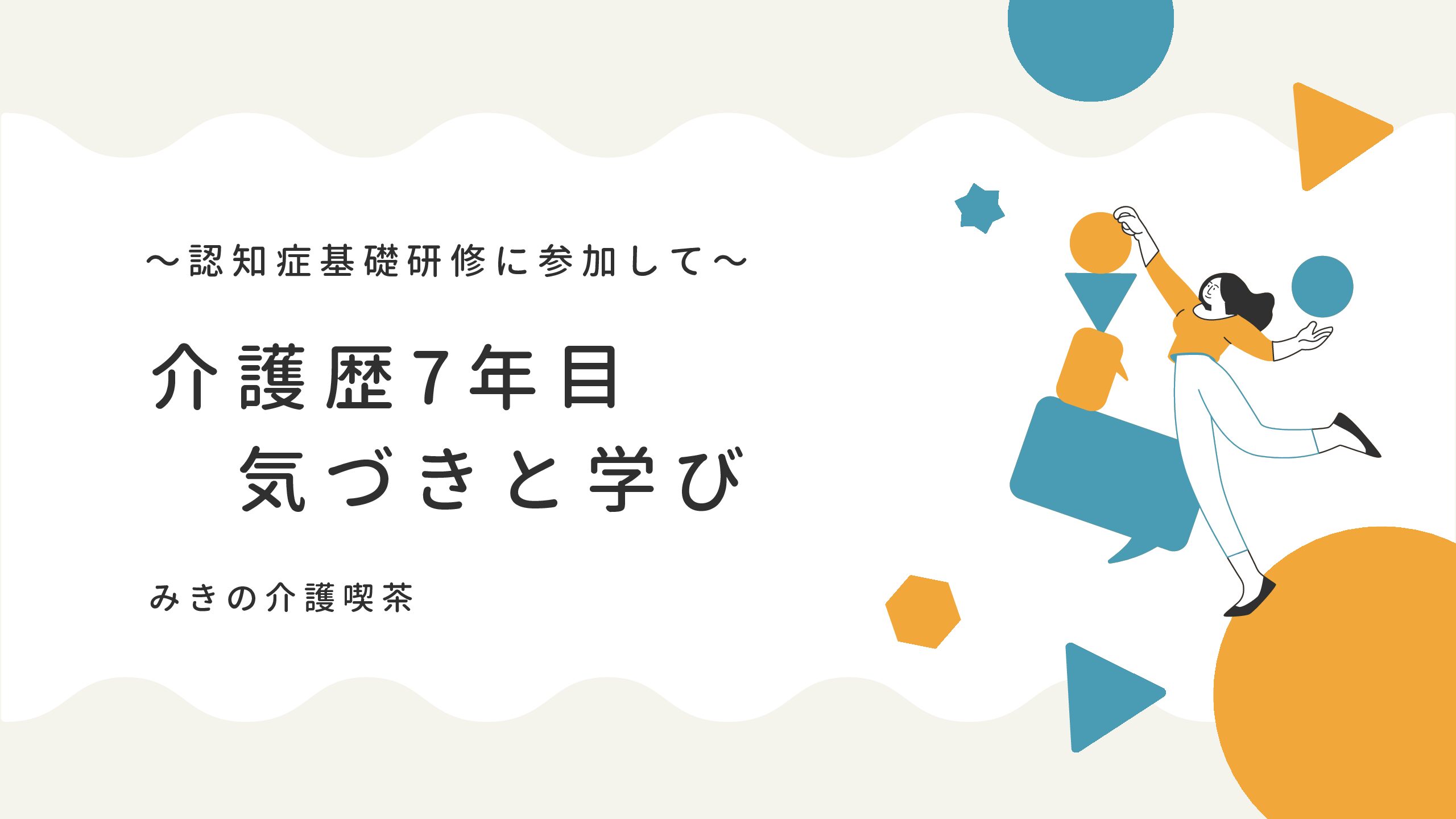
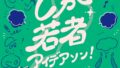
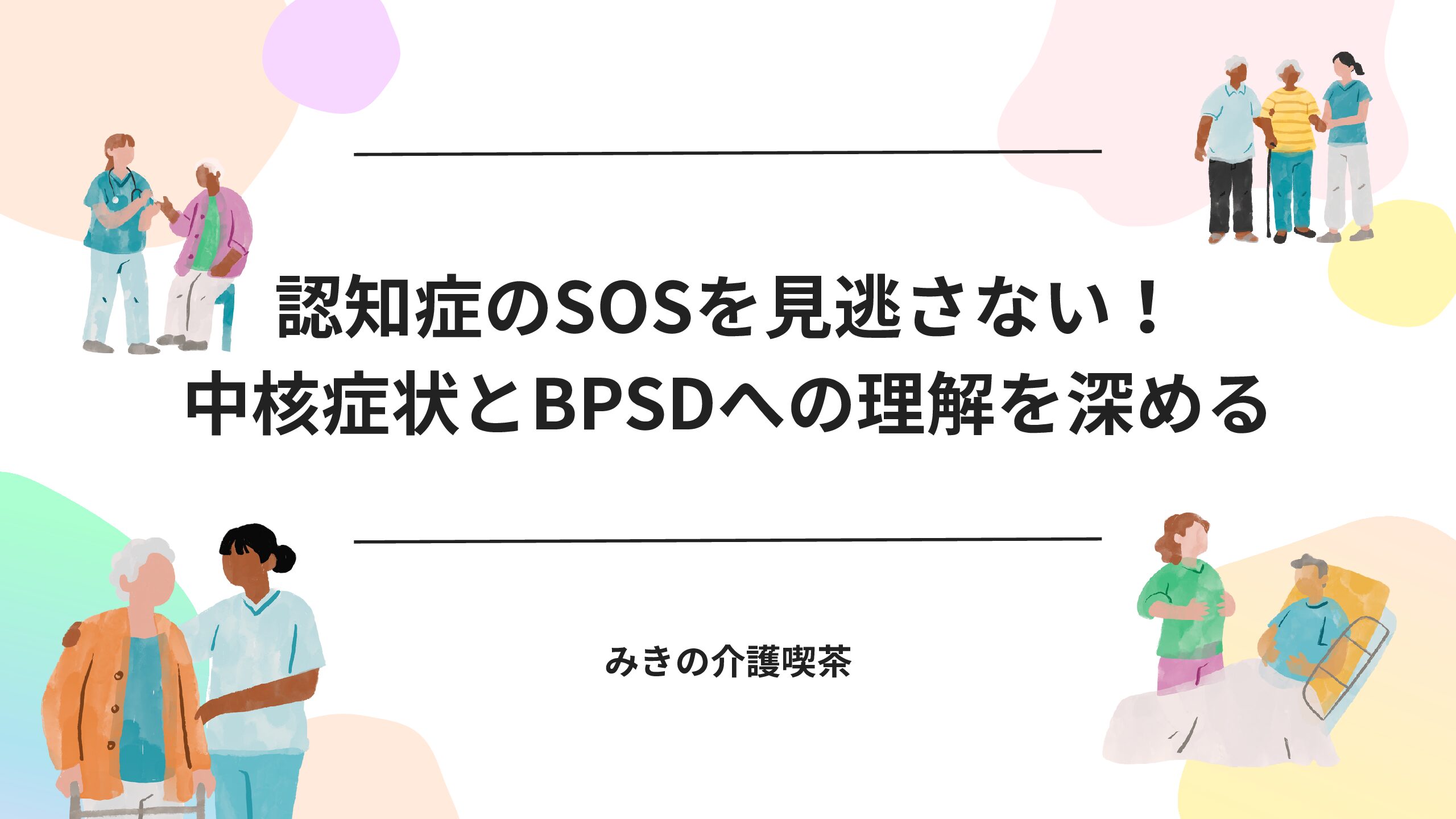
コメント